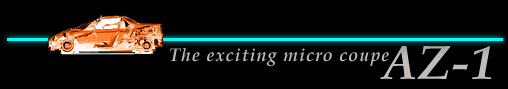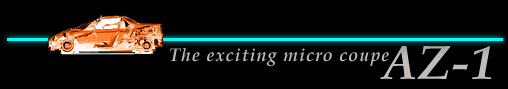
誓約書に対する各人の考え方(地裁での口頭弁論)
ちょっと時系列がおかしくなるのだが、地裁での口頭弁論で行われた誓約書に対する各人の考え方について紹介したい。紹介する文面は裁判所に保管されている「第2分類・証拠調べ調書群・嘱託解答書群」に記載されているものから抜粋しており、地裁での第21回口頭弁論の時に出てきた証言と思われる。これと、後述のFISCO担当弁護士との対談をもとに、各人どうすべきか考えて欲しい。
太田選手の場合
注)指示代名詞が多いが、これは私のタイプミスではない。
Q.例えばドライバーだったらあの契約は成り立つと?
A.ドライバー同士だったらということではなく、ドライバー同士、主催者同士であってもここまではその規定をはめよう、だけど最後の部分のどうしようもない部分というか、そこの部分に関してまでやるとなると、あの例えばJAFの規定とか誓約書が何をやってもそれは超法規だとなると、要はあくまでも死の誓約書になるっていう。
それは逆に言えば、ぼくにすれば、その死の誓約書っていうことでは思って無くて、それだけ安全装備をやるっていう趣旨だと思ったんですけども、でもそうじゃなくて、それが裏返しになって、何やっても主催者は責任をとれないっていう、要は悪魔の誓約書に取り変わったっていうのが、今回の問題だということを思っています。
Q.今後ああいう誓約書を要求されたときには、あなたはどうされますか。
A.これは、だからぜひJAFの方と主催者の方でよく話し合っていただきたいですけど、あくまでもレース界の常識は日本の常識とかけ離れたところにあるんではなくて、日本の常識っていうベースの上にレース界の常識があるっていうことを、もう一度話し合いをしていただきたいと思います。
Q.あなた個人としてはどうされますか。誓約書にサインしてくれと言われたら拒否しますか。
A.そこのところで、これは話し合われた上で、あれはあくまでもスポーツの一部を規定する規則であり、日本の常識はあくまでもレース界にも常識が入ると言うことになれば、ぼくは喜んでサインをさせていただきたいと思います。
Q.それまではサインしないと言うことですか。
A.サインは出来ないんじゃないと思います。そういう意味でレースへ戻れないのかなっていう。
---- 記録によると、以下は上記証言より先に述べられているが、本稿での話の流れから順番を逆にする。 ----
Q.事故後、レースとして参加されたことはないのですか。
A.はい、レースというものはJAFのレースだけがレースっていう風に解釈していますから。
Q.レースはJAFとは関係無しに出来ないでしょう。
A.いやそれはレースという名称は使っちゃいけないと。走行会形式の競技会というような言い方をします。
Q.その際、主催者とかサーキットから、事故があっても関係者には責任追及しないという誓約書を取られますね。
A.いや、ぼくは書きませんでした。
Q.要求はされた?
A.いや、されませんでした。
Q.要求もされなかったんですか。
A.はい、事情はみんな知ってますから。
砂子選手の場合
Q.あなたは今回、追突事故を起こすと同時に激突されたというお立場ですけども、この物損とか損害、治療費とかそういうものについて、どなたかに請求されましたか。
A.してません。
Q.チームの代表の方が主催者、加害者と思われる方に損害賠償とかいう請求をしたことはありますか。
A.してないと思います。
Q.あなたはレースに参加するにあたって、誓約書といものに署名することはご存じですね。
A.はい
Q.誓約書についてどう思われますか
A.非常に形式的なものだったと思います。
Q.あなたは誓約書に書いてあることを守ろうという意識はないんですか。要するに一言で言えば、他のドライバーを訴えたりしないとか、主催者とか役員、オフィシャルの方とか、そういう方を訴えないという趣旨ですね。そういう誓約書の無いようについて守ろうと、署名された時にこれは守ろうと、お互いに守ろうというという気持ちはないんですか。
A.守ろうというか、いろんな意味で自己責任はあると思います。でもあなたにも自己責任がある。皆さん自己責任がある。ですからドライバーだけが自己責任というのはおかしな話です。いろんな方に自己責任があるはずです。
Q.今、自己責任と言う言葉を使われましたね。
A.はい
Q.ドライバーにも自己責任があると思うと。でもそれはドライバーだけではないと言う意味で、みんなにあると言ったんですね。
A.そうですね。レースを司る人たち、それぞれに自己責任があると思います。
Q.ドライバーだけが責任を問われると言う理屈はおかしいと言いたいのですか。
A.そうです。
太田選手と砂子選手の弁論を比較すると、太田選手の方が何を言っているのかさっぱりわからないと思うが、これには理由がある。砂子選手の方は「当事者尋問」即ち、太田選手側の弁護士が砂子選手に聞いているためだ。要はあらかじめうち合わせておいた話を裁判の場で筋書き通りにに言っているだけだから、的確な受け答えが出来ているのだ。
対して太田選手の場合は「反対尋問」即ち、FISCO側の弁護士が太田選手に聞いている。質問される内容があらかじめ分かっていないため、答える時にしどろもどろになっているのだ。しかしそれを割り引いても、何がいいたいのかさっぱり分からない(不満があるのだけは理解できる)。前頁で「なおスタートかどうかの判断についての被控訴人(太田選手)の証言は、前半部分では支離滅裂である(同調書53〜55)こと付言する。」と書いていたが、恐らくこのような状態であったものと推察される。この証言をタイプした書記官もさることながら、何を言わんとするか必死に解釈して判決を出さなければならない裁判官もご苦労なことである。
それにしても、この裁判で根幹をなす部分の考えが自分なりにまとまっていないのに裁判を起こすというのは疑問である。FISCOとしては不明確な目撃証言だけで訴えられたようなものであろう。また誓約書を出さない=もし事故したら責任の所在がどうであれ裁判を起こして揉ましまくる可能性のある人間をサーキットで走らせるという走行会の主催者の神経が理解できない。そもそも本人も、事故した(失敗した)原因追及と対策を施さない状態で走行会に出ること自体が世間一般では考えられない。対策せずして挑戦しても、また失敗するだけである。そうでしょ。
砂子選手が「ドライバーだけが責任を問われると言う理屈はおかしいと言いたい」との旨の証言をしているが、これは全然おかしくない。なぜなら誓約書を取り交わしているからである。「私的自治の自由」というものがあり、どんな誓約や契約を結ぼうと双方の勝手なのである。どんな値段を付けて物を売り買いしようが当事者の自由であるのと同じだ。誓約書を受け入れた以上、理屈はおかしくない。これが法治国家日本の常識であり、その上になんでも成り立っているのだ。ただし、「ミスをしたら罰として殺す」とかいう誓約なり契約は他の法律によって許されないため、私的自治の自由の拡大解釈を制限できる。今回の裁判の場合、レースの誓約書において「私的自治の自由」を適切に制限する法律が存在しなかったため、何をもって・どこで線を引くかが揉めたとも言える(結論としては、経済的利益を一方的に得ているか否かで線が引かれた)。