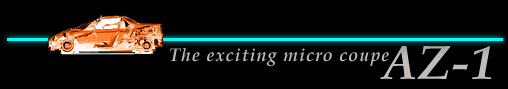
冒頭述べたとおり、この裁判は東京高裁で和解が成立している。和解とは双方の歩み寄りで成立するもので、裁判所を通じた示談だと考えて欲しい。
和解までに至った経緯を述べよう。結論からいうと「収拾のつかない泥仕合になったため」である。
順を追って説明しよう。最初に控訴の趣旨について記す。これは控訴人(FISCO等)が地裁判決を不服として申し立てたものである。
1.原判決(地裁でFISCO側が負けた判決)中、FISCO、FISCOクラブの各敗訴部分をそれぞれ取り消す。
2.被控訴人(太田選手側)の控訴人FISCO及びFISCOクラブに対する各請求をいずれも棄却する。
3.訴訟費用は第一審、第二審とも被控訴人の負担とする。
との判決を求める。
また我々にとっても重要な、地裁判決の誓約書に関する部分への反論だが、以下のように書かれてあった。
レースでは、ドライバーによって重大な事故が発生した場合、レースの中止を余儀なくされ、設備を破壊されれも事故を起こしたドライバーに対して損害の賠償を請求できないのであるから、主催者だけが一方的に利益を得て「いい目」をみているわけではない。 モータースポーツは全ての競技参加者の相互免責の上に成り立っている。
以上のような申し立てに基づき、平成16年1月29日に高裁での第一回目の公判がひらかれ、1年を経過した平成17年2月8日に弁論が終結すると同時に裁判所から和解勧告がだされた。それから半年後の平成17年7月28日に和解が成立し、本事案は全て決着した。
なお決着するまでの1年間、「なおスタートかどうかの判断についての被控訴人(太田選手)の証言は、前半部分では支離滅裂である(同調書53〜55)こと付言する。」とか「控訴人(FISCO)らの主張は瑣末(さまつ)な事実にかこつけて責任回避の理屈をひねり出そうとする卑劣な主張と言うほかはないと批判している。しかし上記批判が品位を欠く批判であることはともかくとして・・・」とかいうやりとりが行われ、泥仕合の様相を呈してきた。そこで和解勧告が出されたのであった。
次に和解条項について記す。これが高裁の判決だと考えてもらっていい。原文はA4 1枚の紙に書かれている。
和解条項
1.控訴人富士スピードウエイ、同富士モータースポーツクラブ、日本モーターレーシングセンター、ビクトリーサークルクラブ、中村、テレビ東京は、被控訴人に対し本件和解金として連帯して9000万円の支払い義務のあることを認める。
2.金員は連帯して振り込め。
3.振り込みを怠った場合、年10%の遅延賠償金を付加して直ちに支払う。
4.控訴人らは第一項の債務についての内部負担割合を次の通りとする。
(1)富士スピードウエイ、富士モータースポーツクラブ 連帯して1/3
(2)日本モーターレーシングセンター、ビクトリーサークルクラブ、中村 連帯して1/3
(3)テレビ東京 1/3
5.被控訴人は、控訴人富士スピードウエイを申立人とし、被控訴人を被申立人とする東京地裁平成15年(モ)14847号強制執行停止決定申立事件について、被控訴人富士スピードウエイが平成15年11月18日に供託した担保金7000万円の担保取り消しに同意し、かつその取り消し決定に対する即時抗告権を放棄する。
6.被控訴人は、控訴人らに対する、その余の請求を放棄する。
7.被控訴人と控訴人らは本和解条項に定める他に何らの債権債務のないことを相互に確認する。
8.訴訟費用及び和解費用は、第一、第2審を通じて、各自の負担とする。
以上でこの裁判は終結した。さんざんやった挙げ句の果てが、紙1枚である。この紙1枚の結論に達するために、前回紹介した5万字の判決が必要だったことは間違いないのだが、むなしい。こんなことでもめるのなら、最初から走らなければ済んだことだ。自動車趣味的に言うと、一番重要な「誓約書」の部分に関する言及がない。本裁判で一番とばっちりを食らったのは我々アマチュアなのだが、この和解条は我々にとって価値あるものを何ももたらしてはくれていない。となると、自らが主体的に動いて価値あるものを探しに行く。