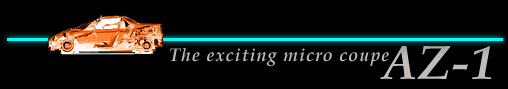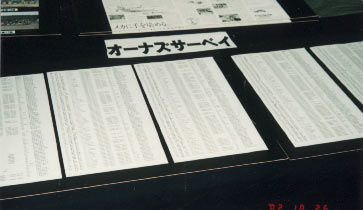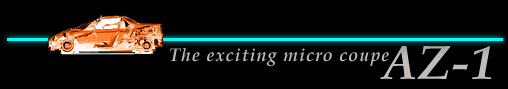
旧車のクラブの活動
1)パーツの流通について
随分前にはホンダ旧車のパーツ供給は良く、その後「あるけど合わないし高い」時期を経て現在「無い」に至っています。インターネット普及前は情報も不足がちで、そのため不安にかられて買い置きされて死蔵したパーツが沢山ありました。一方パーツ難から不動状態の車も出て、それを打開するために「物々交換」主体の「ザ、パーツ」が行われてきました。

これは要するにイベント当日の広告壁新聞のようなもので、「同じ値段なら沢山出品した人(パーツを沢山吐き出した人)が優先」という面白いルールがありました。現在も行われていますが、こっちのほうは最早使命を終えつつあります。なんといっても情報が古い。ヤフーオークションなどにとって代わられるのは時間の問題でしょう。まぁ、インターネット以前にこのようなものがあったということは評価されるべきでしょう。
2)技術の伝承
エスは「火の玉のように熱い創業者=本田宗一郎」のかかわった車として、あるいはモータースポーツ草創期をリードした車として評価が高いため、古くから「ホンダスポーツ」関連書籍が沢山出版されてきました。(二玄社、三樹書房、芸文社等)またパーツリストや整備解説書についても「単なる収集目的」のオリジナル本のほかに、実用的なコピー本、海賊本が多数流通しています(こちらは安価)。これらを丹念に目を通すことで一通りの歴史や構造を知る事ができます。この他、熱心なマニアがガリ版刷りで残した冊子(これについては次回番外編で紹介します)やここに示すツインカムクラブのちょっとした冊子(GARAGE)などもあります。

これらは主観が入りますが一方では整備書の間違いを指摘していたりして面白いです。なおこれは現在クラブのHP内に再構築中(http://www02.so-net.ne.jp/~honda-s/garage/garage_01.html)で、近い将来ネット上に保存され誰でも閲覧可能になることでしょう。さらにはこの分野では製造元のHONDAは積極的で、メーカーのHP上に「バーチャルピット」と呼ばれるページがあり(http://www.honda-vp.com/vpit/servlet/honda.Login1)整備解説書、パーツリスト等を閲覧できます。こちらについてはオールドタイマー誌Vol.67を参照ください。
3)オーナーズサーベイ
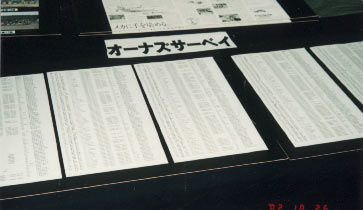
これはAZ−1オーナーリスト(旧リスト化計画)とほぼ同じものです。エンジン番号も調査されています。前に述べたように、エス「シリーズ」は実に多くの設計変更を繰り返した為に、車体番号の少しの違いで全くパーツが合わなかったり、入手した車が違うロットのパーツをまぜこぜや無理やり組まれた車が多いこともあっていろんな難儀なことが起こります。レストアをする上で「新車復元」にこだわるならば充分な調査と勉強が必要で、時には車体番号が近隣の素性のはっきりした車を見せてもらったりも必要でしょう。こういった場合に威力を発揮します。また得体のしれない欠番や海外輸出組のことなど、考古学的な調査に魅せられたマニアも多いようです。
4)市川さんから谷村会長への質問
このイベントを第1回から企画、運営してきた大阪のツインカムクラブの会長、谷村憲造氏に質問をぶつけてみました。実は7つあったのですが、あとのものは今回のレポートの内容と重複しますので省略しました。以下はその回答メールから。
スズカでもお話ししたように大層に考えてクラブやスズカ大会をやってきたわけではないので、あまり偉そうなことは言えません。ひたすらエスが好きでそれに夢中になり、またその仲間達と楽しければいい、その考えのみです。エスのパワーが全ての様な気がします。どうしてもと、いうことでご返事させていただければ、
1.クラブ活性化方法
長くやっていると、マンネリ化してきます。その防止法に何か参考になるものがあれば。
A.逆にマンネリがいいと思います。
2.クラブ構成員の若返り策
AZ−1の場合も古いオーナーがたくさんいて、いずれは高齢化社会を迎えるでしょう。何か参考になる若返り策に取り組まれていれば。
A.年令は確かに問題ですが、young at heart でいいと思います。年寄りは、年寄りなりにいいですし、若い方が新しい感覚で参加されるのもいいのではないでしょうか。片寄りそうな構成ですが。
3.若いクラブ員の教育法
1と関係しますが、何かあれば。AZ−1の場合は、まずは向上心をもたせること、次に希少絶版車のオーナーとしての自覚を持たせることでしょうか。
A.想いのない方には何をやっても無理な様な気がします。自然体でいいのではないでしょうか。全てはそのクルマが支えるものだと思いますが。それが長く続くことでメンバー間で信頼や親戚の様な近さが生まれるのかも知れません。
AZ-1もすばらしいクルマでエスと同じで、まず他にない種だと思います。クルマに寄せる想いがあればある程それは、より未来へ受け継がれてゆくのかなと思います。
こんなところですが、ご参考になりましたでしょうか。
ホンダツインカムクラブ事務局 谷村 憲造
まぁ、車自体に魅力がありさえすれば、あとは自然体でなんとかなるということでしょう。無理やり変えようとしなくとも。