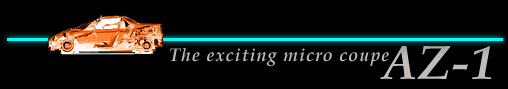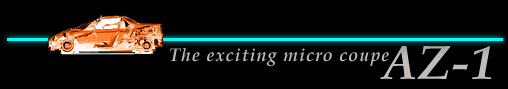
F1の模擬レース
この佃煮2、以前もお伝えしたとおりK-carミーティングと併設されて行われた。で、そのK-carミーティングの出し物の1つとして行われたのが、F1の模擬レースだ。当日走行したF1は4台。ただしこれらは現役バリバリのマシンではない。ロータス78を始め、4台の古いF1達だ。じゃ、ドライバーは誰ということになるのだが、これがまた凄い。F1のオーナー自らが操っているというのだ。ここに集まった4台のF1はみんな個人で所有しているものだそうだ。なんという贅沢な趣味。いったいどういう連中なのか、他にどんな車を持っているのか聞いてみたいものだ。
 |
 |
| ロータス78 |
アルファロメオ178B |

下:マーチ811、上:ベネトンB188
ここで個人的に一番すきなロータス78について紹介したい。解説は、魅巣亭のHPのポーラ・ベアーさんだ。その中にF1のコーナーがあるので、興味のある人は行ってみよう。
ロータス78
このマシンは、コーリン・チャップマン率いるチーム・ロータスの、第三期黄金時代の足がかりになった記念すべきマシンであり、また、近代F1マシン及び、あらゆるカテゴリーのマシンのエアロダイナミックスに旋風を巻き起こし、一つの時代を築く「礎」になったマシンとも言えると思う。
これまでは、マシンのボディー上面を流れる空気を、いかにスムーズに流すかによって「ストレートスピードのアップ」を図るか、また、それとは逆に、いかにして強力なダウンフォースを得るかによって「コーナーリングスピードのアップ」を図るか、という相反する二つのテーマについてどう妥協させるか、また、どうバランスをとるるかが、各チームのデザイナーの腕の見せ所でもあり、悩みの種でもあった訳である。
このロータス78は、空気をいかに進入させないかで苦労していたボディーの下面に、積極的に空気をとり入れるという、言わば発想の転換を図ったマシンでもある。設計者は、C.チャップマンをチーフにP.ライト、R.ベラミー、他のメンバー(T.サウスゲートも居たが、彼の後のマシンのデザインからは、どうも「グランドエフェクト」を理解していたとは思えない)で開発されたと言われる。特にP.ライトは、マーチ在籍時代のマシンデザインからも判るように、サイドポンツーンの形状と逆揚力には、ただならぬ関心があったようだ。
その着目点とは、サイドポンツーン下面を逆翼断面状に成形し、路面との隙間を部分的に狭くし、流れてきた空気の流速を速めることによりサイドポンツーン自体と路面との間で、一時的な負圧を生じさせ「ベンチュリー効果」を狙うという、これまでの常識を覆すものだった。更にサイドポンツーン両サイドを、「スカート」と呼ばれたシュロ製のブラシで、サイドポンツーン下側を流れる空気とマシンの外部を流れる空気を遮断しその効果を高めようとしていた。
当時は、グランドエフェクトカー、ウイングカー、ベンチュリーカーなどといろんな呼び方をされていたようだが、ロータス78は正確にはグランドエフェクトカーと呼ばれ、いわゆる、その後のウイングカーの草分け的存在となったマシンでもある。ただ、チームロータスが、この革新的なアイディアで成功を収めるのは、「78」を技術的に更に新化させた後継マシンである、「ロータス79」まで待たなければならなかった。前後のサスペンションを始めとする、「空気の流れ」をよりスムーズにすることと、逆揚力の発生ポイントの追及等の未知なる課題を解決する必要があったわけである。
また、このマシンは’78イタリアGPにおいて事故死した(手術のミスともいわれている)、「サイドウェイ・ロニー」ことロニー・ピーターソンが、最期にグランプリに出走した悲劇のマシン(同型)でもある。
この年、ティレルより古巣のロータスに戻ったピーターソンは、ロータス79にて同僚のM.アンドレッティーと共に、16戦中8勝という圧倒的な勝利を挙げ、二人でタイトルを争っていたわけだが、ピーターソンはイタリアGPの予選でトラブルが発生した「79」に替え、この「78」で決勝レースに出走している。この「78」は「79」と違い、サイドポンツーン内に燃料を分割積載しており、スタート直後の多重クラッシュによりタンクが潰れ、被害を甚大なものにしたとも言われている。仮に燃料をセンターバック搭載にしていた「79」であれば、あるいは、ピーターソンは死なずに済んでいたかもしれないと言われた。ピーターソンの死により同僚のアンドレティーのタイトル獲得が決定したという、暗い記録も残っている。
今回の写真のマシンは、「HF1DC」副会長の西田氏所有のマシンであると、一部の車の雑誌に掲載され「’77日本GPのG.ニールソン車」と紹介されていたが、残念ながら当時のマシンのオリジナル状態ではないようである。(ロール・オーバーバーとリアウイングのステー及びその形状が改良?されているようである)できることなら、オリジナルの姿で保存してもらいたいものである。

模擬レースはコースを1周してそれから停車せずにスタートするローリングスタートであった。富士スピードウエイに久々に轟くF1の爆音(と、はじめは思っていたのだが、よく調べてみると直近では99年10月17日に行われたJCCA主催の「くるま祭り」で走っていた)。私自身はF1が走るところをテレビ以外で見たことはないのだが、F1の約10倍の出力(約5000馬力)を誇るドラッグレースの車なら見たことがある。ドラッグレースの場合は通常2台で走行するため併せて1万馬力。F1は4台併せて単純計算で4000馬力だから大きな音はしないのだろうと思っていたのだが、さにあらず。結構な音がした。これが20台以上走る本物のレースだったらどれだけすごい音になるのだろうか。想像がつかない。ちなみにタイムは約1分30秒。さてこのタイムだが、先ほど紹介したスプリントレースで優勝したAZ−1の出したタイムが2分ちょうどだったので、F1が速いというべきなのか、それともAZ−1もなかなかやると言うべきなのか・・・
またこの模擬レースにはもう1ついいことがあった。観客が非常に少なかったという点である。通常では大勢のマスコミやファンの発する怒号・罵声がせっかくのF1サウンドをかき消して、細かい音まで聞き分けることが出来ない。しかしである、今回メインスタンドに集まった観客はせいぜい100人。話し声など全くと言っていいほど聞こえなかった。普通なら「誰もいないサーキットにF1サウンドがむなしく響き渡った」と書くところだが、ここは1つ「誰もいないサーキットでF1サウンドを独り占めした」と表現したい。ここまでクリアにF1サウンドを聴くチャンスをものにすることができたという世界でもまれな出来事に感動したいと思う。