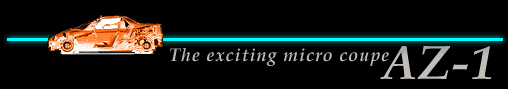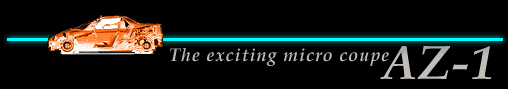
マツダ 優勝までの軌跡
提供していただいた資料より抜粋した。
'88
ホンダスーパーカブ50CCエンジンを搭載した世界最小の前面投影面積(0.165m2)、小径ホイール(16インチ)の特徴をもつ超軽量車両(18kg)を若手社員4名で製作、初出場ながら10位入賞/427台 600km/リットル。
'89
小型エンジンの泣き所である冷却損失と抵抗損失の大幅な低減を狙った真球型の燃焼室をもつ超ロングストローク30ccの完全自作エンジンを開発。また、エネルギー回収装置(フライホイール)も同時に開発。さらに性能テスト用シャーシローラーも製作。毎晩徹夜作業をしたがそれでも時間が足りず、完成度が低いままレースに出場した。結果は効果未確認のまま出場したフライホイールが逆に抵抗となり、自作エンジンもトラブルを起こした。リタイヤ/396台。
'90
エンジントラブルの原因がクランク系とわかり対策を行ったが、部品が間に合わず旧型('88年車)で出場。また、マイレッジ専用のサーキットシミュレーションを完成させた。13位/431台。 493km/リットル。
'91
エンジン不具合が直ったので、さらに燃料の制御性を上げるべく電子制御フィードバックキャブレターの開発を行った。またエンジンテストベンチも廃品のトルクメーターをもらって自前で製作した。しかしコンピューターのデバッグが間に合わず、制御トラブルを起こし41位/429台。 378km/リットル。
'92
経験豊富な男性ドライバー(45kg!)を起用し、燃料制御系は酸素センサーの出力電圧値をドライバーが目で見て、手動で空燃比を制御する方法に変更した。これにより、複雑で重量のあるシステムを計量でかつ信頼性の高いものにすることができた。レースは自己最高の2位/507台 704km/リットルとなった。
'93
ヘリウム封入というアイディアでエネルギー回収装置(フライホイール)を再開発した。これによりフライホイール自体の空気抵抗は大幅に低減できたが、動力の入出力でのロスがまだまだ大きく、結局お蔵入り。またそれと並行して走行抵抗の大幅な低減をめざし、新型車の開発を開始したが、これもレースに間に合わず、昨年の車両で出場。雨天による伝送系のトラブルでリタイヤ/551台。
'94
風洞実験を何度も繰り返し行った空力ボディー(Cd=0.12)と、マイレッジ専用に開発したミシュラン製 超低抵抗タイヤ(ur=0.0023)を装着した新型車を完成させてレースに挑んだ。ところがスピンした車両を避けてコースアウトし、タイヤがバースト。リタイヤ/546台。ただし、技術の高さが評価され、AXIS賞を受賞。
'95
エンジンをEGIに変更し、燃料の制御性を高め、空力もリヤアンダーカウルの装着により改善を図った。テストデータからシミュレーションすると1200km/リットル以上が期待でき、この年から優勝&日本記録を本気で意識するようになった。しかし、結果は新たに装着したリヤアンダーカウルがタイヤと干渉し、3位/600台。 884km/リットルにとどまった。
'96
昨年の不具合を全て対策し、始動性を向上させる制御ロジックも取り入れてレースに臨んだ。台風17号の通過により強風が吹き荒れ、ドライビングに苦労したが、念願の優勝を勝ち取った。995km/リットル 1位/533台。