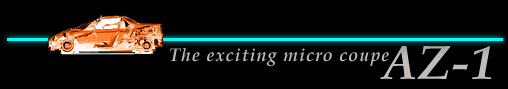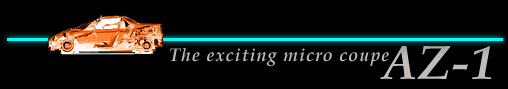
似て非なるもの、ケーターハムスーパーセブンとバーキン7
というわけで、Sr.3を原型としてさまざまなセブンが作られた。ケーターハム、バーキン、ウエストフィールド、フレイザー、ドンカーブート、シュペールマルタン、タイガー、いわゆるカナディアン、日本からは光岡のゼロワンがあった。
これらのセブン一族(?)の中で一大勢力として2分するのがケーターハムとバーキンである。両社は「どちらがロータスセブンの正当な後継者か?」ということで半ば泥仕合になったことがあった。特にバーキン側の露骨な比較広告には笑えるのだが、このあたりの話は別の機会に譲るとして、まずはどちらがケーターハムで、どちらがバーキンなのか当てていただきましょう。
う〜ん、どっちがどっちかわからんですなあ。答えは左がバーキン、右がケーターハムである。実は簡単な見分け方があるのだ。まず注目してもらいたいのはロアアームである。ここの形状がちょっと違うのだ。バーキンには矢印の棒があるのだが、ケーターハムにはない。
なぜこのような違いがあるかというと、ケーターハムとバーキンの生い立ちの違いをみればわかる。バーキンはケーターハムの悪いところを修正して作られたのだ。というわけで、補強材が入っているというわけである。
次に分かりやすいのがロールバー。ロールバーの付け根がトランクの中に入っているのがケーターハム、入っていないのがバーキンである。これも、トランクを広く使うためにバーキンでは改良されているのだ。
なお、このやり方ではその他ウエストフィールドとかフレイザーとかを見分けることはできない。

こちらはケーターハムね
それにしても今回はセブン系の車が少なかった。あれだけあった車はいったいどこへ消えたんだ??
中古自動車雑誌やヤフオクをみると、気になるデータがある。トリップメーターが正しいとするならば、セブン系の車は1オーナーあたり3000〜5000kmでお払い箱になっているのだ。3000kmで売るくらいなら始めから買うなよと言いたくなる数字である。
算出の方法は簡単。オークションに書かれている走行距離をオーナー数で割るのだ。オーナー数は「複数」と書かれていることが多い。1オーナーで売る場合は明らかに売り手が1代目であることがわかるはず。「複数」とは正確には2オーナー目も含むが、前オーナーからの引継で2オーナー目であることはほぼ間違いなくわかるはずだ。よってオーナー数がわけわからなくなりはじめるのは3オーナー目からとなる。そこで走行距離を3で割ると、1オーナーあたり3000〜5000kmとなる。
もちろん全ての車が3000kmでお払い箱になるわけではない。こうまであっさり手放してしまうのは、車に魅力がないからではない。こんな車を持つことに対する新規オーナーの自覚のなさに問題がある。ここで散々文句を書いたところで、文句を言うべき対象は既にセブンを降りているので、いろいろ書いても仕方ないのだが・・・ただし、あえていうなら無責任なオーナーを増やすために存在するかのような自動車雑誌の煽り記事の存在、無責任なオーナーの増加を未然に防ぐための有効な策が存在しない点、不便な車にもかかわらず乗らなければならない明確な理由を持つ人に対する各種のサポート体制が十分に構築できていない点についてはベテランオーナーの責任なのかもしれない(じゃあどうすりゃいいんだ、という人はこちらを参照)。すぐに手放すオーナーは、扱いきれなくなったという理由でペットを山に捨てる飼い主と同じである。こういう車がひどい仕打ちを受ける現状は、非常に残念でならない。